1408 views
本を読む本
ハウツー本として紹介したい本の1冊目は「本を読む本」です。
M.J.アドラー / C.V.ドレーン著(1997)「本を読む本」,講談社
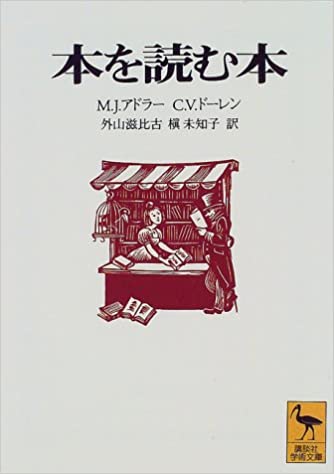
どのような本か?
読書のレベル
この本では、読書のレベルには
1. 初級読書(読み書きのまったくできない子供が初歩の読み書きの技術を習得するためのもの)
2. 点検読書(系統立てて拾い読みする技術。時間に制約のある場合のもっともすぐれた完璧な読み方)
3. 分析読書(系統だった読書活動。時間に制約のない場合のもっともすぐれた完璧な読み方)
4. シントピカル読書(著者の造語。一冊だけではなく、一つの主題について何冊もの本を相互に関連づけて読むこと)
以上4段階のレベルがあると述べられています。
読むに値するか否か
「本を読む本」は、読むに値する良書を、知的かつ積極的に読むための規則を述べたものであります。すべての本がこの本の奨めるような読みかたに値するわけではありません。
これは本書の冒頭にある「日本の読者の皆さんへ」にある一文です。
この本の奨めるような読みかた=分析読書とシントピカル読書のことですが、すべての本がそれを行うに値するわけではない(逆説的にとらえると、良書以外は拾い読みで十分)というのがこの本の主張です。
「日本人には『本を買ったら最初から最後まで通読するのが常識だ』と考えている人が多く、その結果、『読書は時間がかかるから億劫だ』と避けている人が多い」という話を聞いたことがあります。
皆さんはいかがでしょうか?
お恥ずかしながら、私はこのような考えを持っていたのでこの本を読んだときは大変衝撃を受けました。
もし同じような考えをお持ちの方がいらしゃれば、この本はきっと(良い意味で)パラダイム・シフトを起こしてくれると思います。
是非、お手に取ってご覧頂ければと思います。
Page 1 of 1.
[添付ファイル]
お問い合わせ

Rei Suzuki
自己紹介
都内のICT企業で経営企画DX推進担当として勤務しております。バックオフィス勤務の方向けに業務自動化・効率化をテーマにしたブログを書いております。
本ブログでは仕事以外のことをテーマに色々書いていきたいなと思っております。宜しくお願い致します。
サイト/ブログ
https://backoffice-engineer.hatenablog.com/